1月24日(日) 年賀状友情論
あとし玉付き年賀はがき当選番号が発表された。ここ何年間かは、3等の「選べる有名ブランド食材、地域の特産品」が1本は当るのだが、去年は当らなかった。今年は捲土重来を期して、1等の「選べる海外旅行」でも当てることにしよう。
さて、その年賀状だが、その1枚は、毎年ながら悲喜交々の思いを運んでくれる。『結婚しました。子どもが生まれました』などの明るいお知らせに対して、『訃報』が奥方の名まえで届いたりする。
何年かのやり取りのあった知人友人のうち、音信の途絶えるものが出てくるのも、賀状がもたらす感懐であろう。年に1回、新年の挨拶だけの付き合いしかできない人もたくさん居る。新年に舞い込む1枚のハガキだけが、懐かしい人の息災と近況を伝えるよすがである。
何事にもズボラな僕のことだから、年末の些事に追いまくられて、賀状を投函するのが送れる年も多い。元旦に着かないことも、ここ10年のうちで半分近かったかもしれない。だから相手方も、僕が賀状を省略しようとしているのかと思われたこともあったかもしれないが、賀状が果たす役割の重さを知る僕は、自分からそれを断ち切るようなことはない。今年、賀状が来なかったからと言って、来年は出さないということもない。何かの事情があったのだろうと思うし、出したつもりで居るのかもしれない。
1年や2年、賀状が遅れたからと言って、相手の心を疑うのはそこまでの付き合いしかできないものの証左であろう。僕の友人の中には、学生時代には同じ釜の飯をつついた仲ながら、その後の進学や就職に遠く離れてしまい、以後40数年間、一度も会う機会がない友も何人か居る。しかし、彼らの賀状の行間には、40数年前と何ら変わらぬ友情が光り踊っている。
3年ほども返信のないものは、差し出しては迷惑かと斟酌して、こと人との付き合いに関しては諦めの悪い僕も、さすがに住所録から削除する。『抹消』のボタンを押す指先が、いつも、かすかに痛い。
1月23日(土) 大相撲初場所14日目
北京から帰って、10日ごろに風邪の兆候…。先週には治ったかなと思っていたら、5日ほど前からひどくなって寝込んでしまった。5年ぶりぐらいにひいた風邪…、たまには一日中寝ているのもいいかと思っている。
さて、ずっとベッドにいるものだから、普段はあまり見ないテレビをつけて、大相撲初場所14日目の取り組みを見ていた。
取り組みも14日目になると、来場所の番付に関わる真剣さが取り組みに現れているようで、興味深かった。この一番に勝ち越し負け越しを賭ける取り組みはもちろんだが、9勝と10勝では意味が違う。同様に9敗と10敗でも、来場所の地位は異なる。
豊ノ島は鋭い立会いから、土俵際で詰まった相手をよく見てはたき込んで8勝目。琴奨菊はがっぷり四つになりながら先に攻められて8敗目。負け越しがかかった一番、もっと気持ちを前に出すべきなのではないか。安美錦は華麗なる取り口、立会いぐっと押し込んで、支えようとする相手の力をいなして突き落とし。相手は小結(鶴竜)で、安美錦は前頭6枚目だとはとても思えない一番だった。
把瑠都と柿添の一番はめまぐるしく攻防が変わる展開だったが、最後は把瑠都が捕まえて放り投げた。くやしがる柿添の様子が、大人に負けた子どものようでほほえましい。魁皇対希勢の里戦では、久々に魁皇の右上手の怪力を実感させられた。幕内最多勝はダテではない。
白鵬対琴欧州は、大形力士同士の迫力ある一番だった。そして、朝青龍と日馬富士の結びは朝青龍の優勝がかかった一番。両者十分の立会いからがっぷり四つ、互いにひきつけあう攻防を見せながら、最後は土俵中央での下手投げで、朝青龍の25回目の優勝(歴代3位)が決まった。
相撲が面白くなってきたのは、八百長相撲(無気力相撲と言うのだったか)が減って、一番一番の取り組みに迫力が増したからだろう、その意味でも、貴乃花が果たした役割は大きい。新理事長への立候補を後押ししたいものだ。
1月1日(金、元旦) 明けましておめでとうございます
謹 賀 新 年 . 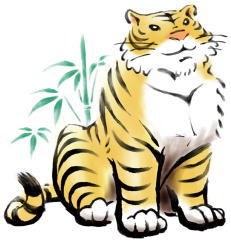 「寅」は「螾」(いん=「動く」の意味)で、 春が来て、草木が生ずる状態を表している。 後に、動物の虎が割り当てられた。 今年も よろしくお願いします。 2010.01.01 |
|---|
西暦(グレゴリオ暦・ユリウス暦)、
2010年が明けた。日本の記年では平
成22年・皇紀2670年、仏滅紀元2
552年閏10月1日-2553年年閏9月
10日、イスラム暦1431年1月15日-
1432年1月24日、ユダヤ暦5770
年4月15日-5771年4月24日となる。
干支は庚寅(かのえ とら)で、陰陽
五行では、十干の庚は陽の金、十二支の
寅は陽の木で、相剋(金剋木)である。
相剋は戦って相手を倒すの意味を持つか
ら、気持ちを引き締めて諸事に当ること
が肝要ということか。
左の賀状にも記したが「寅(いん)」
は「引(ひく)」「伸(のばす)」と同
義語で、庶民に覚えやすいようにと動物
の虎をあてはめたものである。
古来、「寅年」は物事が動くとされて
きた。日本では、政権交代を果たした民
主党が内外の懸案に本格的に取り組む年
であり、夏の参院選で真価を問われるこ
ととなる。
政治の混迷も引き金となって、日本経済の落ち込みはますます深刻なものとなるだろう。安売りの代名詞だったスーパーマーケットがPB商品の開発など更なる安売りを強いられることとなり、下請けや流通・生産者にも原価・経費の削減を求めるデフレスパイラルに入っている。
景気の打開策は見当たらず、まずは政権の維持が最優先の民主党内閣は、財源の確保に目途が立たないままにバラ撒き政策に走っている。38兆円の税収に44兆円の赤字国債…、補正でさらに8兆円を越える借金を重ねようとしていて、膨大な赤字を抱えながら予算の総額は95兆円を超えるという前代未聞の巨額である。国の借金総額は900兆円を突破した。
長期金利の引き上げが生じれば、1%として年間に9兆円が利払いに加算され、3%上がったら27兆円の利子を、現在額に上乗せして支出しなければならない。その結果、借金で借金を返していくという多重債務状態に陥り、国債発行残高が増加の一途をたどるという「借金爆発」の状態に突入してしまう。国の福祉も教育も医療も…、公務員の給料も払えなくなり…、ましてや財政投資や産業の育成など、一切の行政サービスは期待できなくなる。
国の根幹を立て直さねばならない時期を迎えているのだが、政治(政治家)にも、官僚(公務員)にも、大きなリーダーシップを持ち、長期展望を描いて、日本を舵取りするものは、既存の存在の中には見出せない。『百年清河を待つ』のもどかしさを覚えるばかりだが、この時代、個々の力を養い、それを終結する大きなうねりが生じるまで、雌伏の時期を過ごすことだろう。ゆめゆめ忘れてならないことは、この時期にも、個人は力を蓄えることを怠らずに精進することである。
今年、私は、『全ての子どもに学力を』を目指して、新しいプロジェクトをスタートさせる。
このベージのトップへ 飯田 章のHPへ

 2010
2010